
アロマに少し詳しくなると多くの方が使ってみたくなるのが「レモンユーカリオイル」ではないでしょうか。その理由はその強力な「虫除け効果」。
その名前から想像すると、ユーカリのすっきりした香りにレモンの香りが加わったような、そんな香りをイメージしてしまいそうですが、実際は驚くほどに全く違った香り。
その理由は、一般的なユーカリオイルが80%前後の割合で含まれる「1,8シネオール」という成分を中心に構成されているのに対して、レモンユーカリの場合、この成分はごくわずか(2018年現在の出荷ロットEC-068の場合で1.4%)しか含まれていないから。一方でレモンユーカリにはシトロネラールという成分が75%から80%ほど(EC-068の場合で77.7%)含まれていて、成分構成上も香りの上でもこの成分が主軸になっているのですから、香りが全く違っていて当然ですね。
では、このレモンユーカリ、どのような香りがするのか?。名前からは「レモンのような香りのユーカリ」なのですが、これも少し期待はずれ。ちょっと年配の方なら子供の頃に学校などに備え付けられていた固形のレモン石鹸の香りを覚えていらっしゃいませんか? これと似ているため、オーストラリアでも「レモン石鹸みたいな香りだよね」と言われることがあります。
他にたとえるなら山椒の香り。ちょっぴりスパイシーで独特のクセのある香りは山椒の香りに似ているようにも思います。
こんなレモンユーカリですが、蚊が嫌う成分として知られる「シトロネラール」の含有量で他のエッセンシャルオイルを圧倒してダントツの虫除け効果が期待できますから、夏の蚊の増える時期に大活躍。ブレンドなどを工夫することで様々な香りを楽しみにながら、同時に空間の虫除け(殺虫ではありません)ができるのですから、ワクワクしませんか?
アロマを楽しむなら、その機能性で絶対に持っていたいオイルですね。



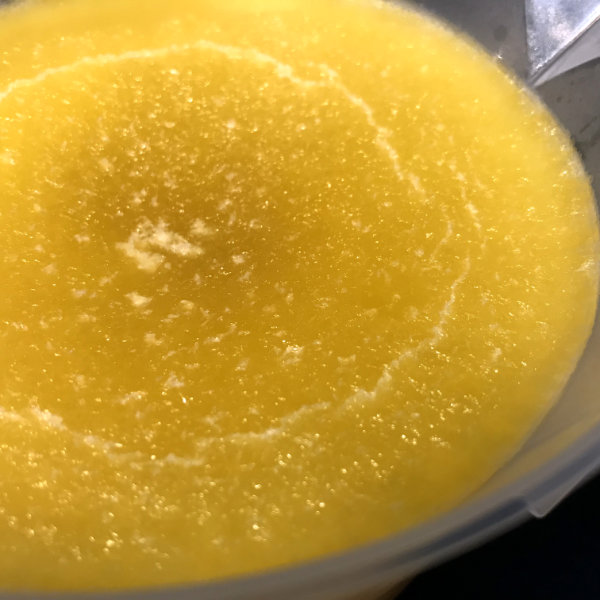









 ところで「メラルーカ」と言うと「
ところで「メラルーカ」と言うと「






